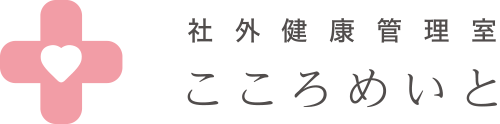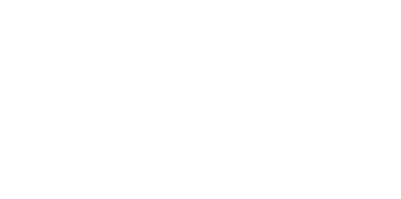役立ち情報
病気治療と職業生活の両立について
日本人の平均寿命が世界一であることをご存じの方も多いでしょう。 寿命が長くなった以外にも、若い世代の人口減少や定年退職後の再雇用制度などの普及によって、年を重ねてからも働く人の数が増えています。 このような現代日本が抱える問題の一つに、病気の治療と仕事の両立があります。 どんな病気にもならないという人はいないでしょう。誰もが年を重ねるにつれ、さまざまな病気を経験することになります。 この記事では、病気の治療と職業生活の両立についてご説明します。 病気を抱える労働者の現況 平成25年に厚生労働省が企業に対して実施したアンケートによれば、病気を理由に1ヶ月以上連続休業している企業の割合は、メンタルヘルスが38%、がんが21%、脳血管疾患が12%となっています。 また、平成22年に行われた国民生活基礎調査に基づく推計によれば、仕事をしながらがんの治療のために通院している人は、32.5万人に上っています。 医療の発展により、かつては治らない病気であったものが「長く付き合う病気」に変化しつつあります。 病気になったからといってすぐに労働者が離職する時代ではなくなりました。 職場が取り組むべき課題 病気を抱えている労働者でも定期的な通院や投薬によって、働きながら治療を続けることが可能なケースも増えています。 しかし、職場の理解や支援の不足により、働きながらの通院が難しい状況が生まれ、離職してしまうケースも存在しています。 労働安全衛生法では、事業者が労働者の健康を確保するための規定があります。 事業者は健康診断の実施や医師との面談を提供し、就業上の措置が必要な場合は、作業場所や内容の変更、労働時間の変更などを行わなくてはなりません。 こうした職場の配慮は、病気を抱える労働者が仕事によって病気の状態を悪くしたり、新たな病気の発症を防ぐために必要なものなのです。 具体的な環境整備 病気を抱える労働者が働きやすい職場づくりのために、環境整備から始めていきましょう。 例えば、時間単位の年次有給休暇制度の導入は、通院してから出社したいというニーズに適しています。 年次有給休暇は基本的には1日単位で与えるのが基本ルールですが、労使協定を結べば1時間単位で与えることが可能になります。 また時差出勤制度を整えることで、通院しやすくなるのはもちろん、ラッシュなど体に負担のかかる時間帯を避けて通勤する環境を用意できます。 同様に在宅ワークも、治療と仕事の両立支援のために導入している企業も増えてきました。 また有給休暇とは別に傷病休暇・病気休暇を設ける企業もあります。 病気治療と職業生活の両立のまとめ ご紹介してきたような治療と仕事の両立支援は、労働者の健康を守るだけでなく労働者の安心感やモチベーションアップにもつながります。 結果、企業としても継続的な人材の確保や、生産性の向上、多様な人材活用が実現できるでしょう。 労働者のワークライフバランスの実現を目指すことが、組織や事業の活性化につながるのです。 誰もが健康で長く働ける社会のために、自分たちができることから取り組んでいきましょう。 参考資料:厚生労働省 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001088186.pdf ココカラ通信10月号
2023.10.31
役立ち情報
災害から身を守る特別警報
今年の夏も、台風や大雨、暴風など自然災害に関連するニュースがたくさんありました。 ニュースで流れる注意報や警報によって、落ち着かない日々を過ごされた方もいらっしゃると思います。 しかし、注意報や警報は私たちが災害から身を守るために必要な情報でもあります。 この記事では、特に私たちが知っておくべき特別警報についてご説明します。 注意報・警報と特別警報の違い 注意報は、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報のことです。 また警報は、重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報のことです。 普段のニュースでもよく耳にするため、雨や台風の多い季節には注意報や警報に慣れてしまう方もいるかもしれませんね。 特別警報は、警報の基準をはるかに超える状態が予想され、重大な災害の起こるおそれが高まっている場合に発表されます。 災害が予想される地域の住民に対して最大級の警戒を呼びかけるものです。 また、区市町村は特別警報を確実に住民に伝えることが義務とされています。 とても重要な情報であることがおわかりいただけることと思います。 特別警報の種類 特別警報には、大きく分けて二つの種類があります。 ①大雨・暴風・高潮・波浪・大雪・暴風雪 これらの災害では、「警報」の発表基準よりもはるかに危険度が高い場合に、「大雨特別警報」、「暴風特別警報」のように「〇〇特別警報」といった名称で発表しています。 台風の時期には、よく耳にする警報ですね。 ②地震・津波・噴火 これらの災害では、危険度が非常に高いレベルのものを「特別警報」としています。 震度6以上の地震予想では「緊急地震速報(警報)」、高さ3m以上の津波予想では「大津波警報」、噴火警戒レベル4以上の予想では「噴火警報(居住地域)」という名称で発表します。 緊急地震速報については、急にニュース画面に出てきたり、スマートフォンから通知が鳴り響いて驚いた経験をお持ちの方も多いと思います。 それだけ、今すぐ住民に知らせなくてはならない重要な情報だということです。 特別警報が発表されたら 特別警報が発表されたときは、まずは決して慌てずに周囲の状況を確認しましょう。 区市町村から避難指示が発令されている場合は、ただちに従ってください。 避難の際に、大雨や暴風のために移動することがかえって危険な状況となっていて自宅などに留まる場合には、二階などのより安全な場所に退避するなど、直ちに身の安全を確保してください。 大雨などは、時間とともに危険度が増す可能性もあります。 すでに避難が完了している場合でも油断をしないようにしましょう。 まとめ 災害時の重要情報である、特別警報についてご説明してきました。 忘れないで頂きたいのは、「特別警報が出ていないから災害は起きない」わけではないということです。 大雨や暴風など気象に関する災害のおそれがあるときは、気象情報や警報、注意報などを活用して、早め早めの避難行動を心がけてください。 参考資料:政府広報オンライン 命を守るために知ってほしい「特別警報」 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201307/4.html ココカラ通信9月号
2023.09.21
役立ち情報
食欲の秋です!
美味しいごはんを食べて元気に過ごそう 〜日本各地の郷土料理〜 郷土料理は、各地域の産物を上手に活用して、風土にあった食べ物として作られています。その地域の歴史や文化、あるいは食生活とともに受け継がれています。郷土料理は、地元で生産されたものを地元で消費する地産地消とともに、子どもたちの食育にも役立っています。 〜中部ブロックの郷土料理〜 日本の真ん中に位置し、山の幸、海の幸が豊富です。 新潟県 きりざい きざんだ野菜と混ぜると、納豆が食べやすい 石川県 じぶ煮 汁にとろみがあるから、肉も野菜も食べやすい 福井県 打ち豆汁 大豆を打ち豆にすると料理に使いやすくなる 山梨県 ほうとう 煮込んだ麺と野菜がまじりあった美味しさ 静岡県 桜えびとしらすのかき揚げ 駿河湾の恵みをいただき、骨を丈夫にする 愛知県 ひきずり ニワトリの飼育がさかんな愛知県のすき焼き 出典、上図引用:農林水産省Webサイト https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/ ココカラ通信9月号
2023.09.05